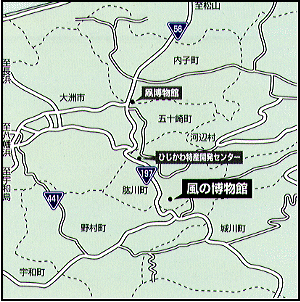

98年から99年にかけて町内の民家等から喜多川歌麿の版木2枚が発見され、全国的にも注目を集めた肱川町は、愛媛の西南地域内陸部にある。この四国山脈の支脈に囲まれた山村では、「風」をキーワードにした町おこし活動を10年以上にわたって繰り広げている。県内各地の町づくりをレポートするシリーズの第1回として、肱川町における「風おこし運動」を紹介する。
さまざまな特産品
国道197号線を大洲・五十崎方面から南にしばらく走ると、左手に「ひじかわ特産開発センター」が見えてくる。ここでは肱川ラーメンなどの食事を提供する他、椎茸、かきもち、よもぎうどん等の即売を行っている。これらの多くは、中居谷(なかいだに)地区(かきもち)、大谷地区(大麦ケーキ)といった地区ごとの「風おこし」が実を結んだものだ。
町内の各地区において、公民館の分館や自治会を中心とした活発な町おこし活動が行われている。正山(しょうざん)地区では、定住者増加のために、地区住民が中心になって宅地造成を行っており(正山風の会)、予小林(よこばやし)地区でも宅地造成の他、花いっぱい運動、独居老人のためのゴミ出しボランティア、河川清掃などに取り組んでいる。そうした活動の中で、特産品開発等の産業振興が図られてきた。
「心に風を」
もともと「風おこし運動」は、町に新しい風(人、もの、情報の交流)を呼び込み、「過疎化に歯止めをかけたい」という町長の発意で、87年に始まった。
肱川町役場を訪ねると、総務課や産業課と並んで「風おこし課」がある。課長の都谷(おがい)さんによれば、運動当初の「風」は「自然の風というより、むしろ住民の活性化を指していた。」「風おこし」が目指すのは、住民1人ひとりが自己革新に向けて心の中に新しい「風」をおこすこと、言い換えると、仮に最初は小さくても、いずれ何か大きな動きにつながる「風」をおこすことだ。「風おこし」には、初期段階の小さなゆらぎが結果に大きな影響を与える、というカオスの原理(※)に近い発想が感じられる。
※
カオス(chaos)に関しては、「北京の1匹の蝶の羽ばたきが、ニューヨークにつむじ風を起こす」
という表現が良く知られている。
「風の博物館」を建設
ただ、こうした「風おこし」の考え方は一般に分かりにくかったため、目に見えるシンボリックな存在が求められた。また、スタートから数年を経て、運動自体のマンネリ化も懸念されるようになってきた。そこで構想されたのが、テーマ館の建設である。
まず、「風」の意味が広がり、心の風であると同時に自然に吹く風、さらには水や太陽光といった自然の力をも象徴するキーワードになった。そして、風に関する色々な資料を収集・展示するほか、住民のコミュニティ機能、情報発信機能などを備えた施設として「風の博物館」がオープンした(94年)。館内の消費電力の一部は、風や太陽の光熱による自家発電で賄われていて、その様子をロビーのディスプレイ上に表示している。自然の風をエネルギー利用できないかと調査したものの十分な風力が得られなかったため、太陽光発電を併用することになったという経緯がある。
96年には、第3回全国風サミットの拠点施設としても活用された。これは、全国の16市町村が参加して毎年開催されるものだ。さらに「風の博物館」は、日本有数の強風地域で知られるえりも町(北海道)の「風の館」や、風と縁の深い凧(たこ)の「凧博物館」(五十崎町)と姉妹館提携を行っている。
「風おこし」は第2ステージへ
「風おこし課」の前の課長・畦崎(うねざき)さんは、公民館の課長として今も「風おこし」に関わる。「産業を振興して雇用の場を作ること、定住人口を増やすことが目標」だという。それぞれの地区から吹き始めた風が、町ぐるみの活性化を実現するうねりになっていくことが理想だ。それは住民の心の活性化であり、自然の恵みを最大限に活かすことによる産業の活性化でもある。
天上界には穏やかで清らかな風が吹くとされている(仏説阿弥陀経)。肱川流域に吹く「風」は、山間(やまあい)の別天地にそよぐ微風(そよかぜ)と呼ぶべきものだ。「風」というコトバにこだわり、そのイメージを膨らまし続けてきた肱川町の「風おこし運動」のさらなる展開が期待される。
(津田 俊生)

風の博物館

